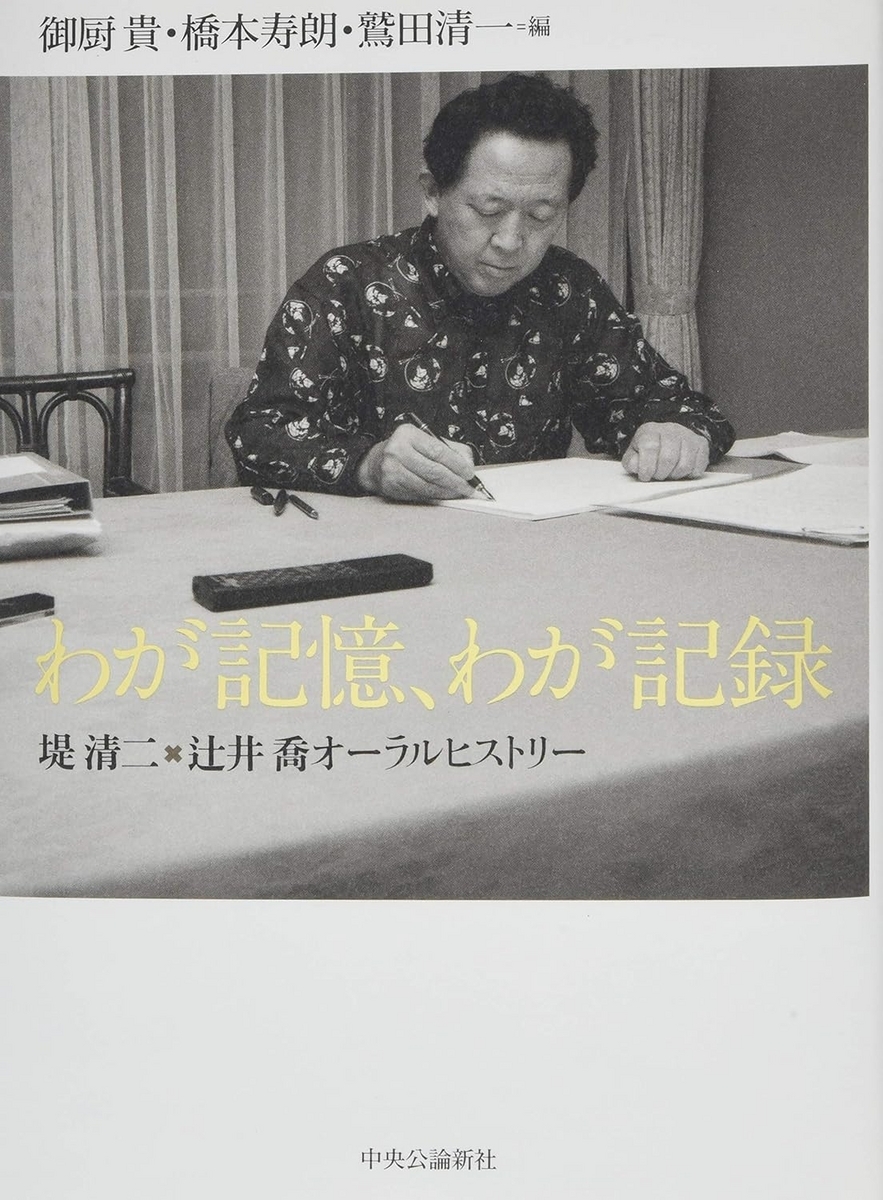
※これ以後、辻井喬=堤清二に関する一連の文章の通しタイトルを「沈める城――辻井喬/堤清二」と致します。
まさに「沈める城」ではないか――辻井喬ではなく、堤清二を追い詰める
御厨貴・橋本寿朗・鷲田清一編『わが記憶、わが記録――堤清二×辻井喬オーラルヒストリー』
■御厨貴・橋本寿朗・鷲田清一編『わが記憶、わが記録――堤清二×辻井喬オーラルヒストリー』2015年11月25日。中央公論新社。
■インタヴュー・座談(流通産業・消費社会・現代史・現代文学)。
■全13回・327頁。
■2024年5月25日読了。
■採点 ★★★★☆。
目次
5 「あれ、私がやっていることは、いったい何だろう。」... 13
1 書籍化を前提としないインタヴュー
本書は、今は亡き、セゾン・グループ代表にして、詩人、小説家である堤清二=辻井喬さんへの、いわば「幻」のインタヴュー集(「オーラルヒストリー」*[1]とされています)の書籍化です。
本企画は、政治学者・御厨(みくりや)貴(たかし)さんを中心として、経済学者・橋本(はしもと)寿(じゅ)朗(ろう)さん、哲学者・鷲田(わしだ)清一(きよかず)さんによるものです。
御厨さんの「あとがき」*[2]をまとめると、次のような経緯があったようです。
- 1990年代頃、オーラルヒストリーの依頼
- 1990年代末、諒承。ただし「記録はとるが整理はせず冊子化しないという厳しい条件つき」*[3]。
- 2000年4月~8月、オーラルヒストリー第1期(第1回から第7回)実施。
- 2000年11月~2001年10月、オーラルヒストリー第2期(第8回~第13回。堤、第2期の整理を拒む*[4]。したがって第2期は堤の手が入っていない*[5])実施。
- 2002年1月、インタヴュワーの一人、橋本寿朗、急逝。
- 2005年1月、第1期分を報告書スタイルとして公にされる*[6]。
- 2015年11月、未定稿であった第2期分も含めて整理し、『わが記憶、わが記録』として公刊。
以上のような次第ですので、あるいは泉下の堤=辻井さんはこの出版を諒とされなかったかも知れませんが、個人的には極めて面白かった、と言わざるを得ません。元々が書籍化を前提にしていないインタヴューだった*[7]こともあり、――到底本人が文章にすることはないだろうと思われる、無尽蔵に裏話の数々が披露されます。
例えば、堤さんの手引きで、首相候補者たち*[8]が密談(?)を、旧堤邸*[9]にて、数回行われたこととか、戦後史の驚くべき事実が明かされたりもします*[10]。
2 辻井喬ではなく、堤清二を追い詰める
無論、そういう側面もありますが、わたしとして興味深かった点は、インタヴュワーの方々のご努力の賜物だと思いますが、類書*[11]に比べて、辻井喬ではなく、堤清二の側面、すなわち、経営面、取り分け西武流通グループに始まり、セゾン・グループの絶頂期と、そしてその急激な凋落の背後を入念に聞き出していることです。
20世紀日本における、流通産業の文化の問題、あるいは、一企業の枠を越えたセゾンという企業群体の意味を考えるに当たって、これは極めて重要かつ、他に替え難い試みであったというべきでしょう。
御厨さんはこう述べています。
月一回という約束で開始。当初は堤さんは硬い表情を崩さず、こちらの質問にメモをとる形で、ゆっくりと考えながら話す趣きであった。だから意外におしゃべりじゃないとの印象をもった。/しかし語り手と聞き手の緊張感は、ツッコミの橋本、ボケの鷲田との応酬の中で、急速になくなっていった。場所はいつも堤さんのフランチャイズで、ホテル西洋銀座、日比谷中日ビル・シーボ二アメンズクラブ、果てはホテルメゾン軽井沢、軽井沢セゾン現代美術館に及んだ。一回二時間が三時間に延長され、夜の時間帯に設定されると酒食も件にするようになった。/これらはすべて普通のオーラル・ヒストリーではご法度(はっと)のことばかりである。しかし我々はツキモノがついたかのようにお互いの距離感をつめていき、二〇〇〇年八月には軽井沢で合宿形式で行うに至った(第五回—第七回)。今冷静に本書を読み返してみると、 オーラル・ヒストリー変じて大シンポジオンの趣きが明らかである。我々三者による切り苛むような質問に、堤さんが受け太刀になりながら、懸命に返り討つさまが、見てとれる。特に文化論ではなく、経営論に絞ったため、〝敗者〟堤清二は、何かに抗うかのように、自らの複層的な思いが、いかにグループ内に浸透しなかったかを、くり返し熱をこめて語った。
(中略)
「辻井喬」 として逃げきろうとする堤さんを、 我々三人は示し合わせたわけではないのに、「堤清二」 に引き戻して追いつめたのである。 その結果、堤さんはこの七回で打ち切りを宣し、速記の整理も活字化もしないとの当初の条件よりは歩み寄ってもらったものの、我々は手入れの後の冊子化で手を打たざるをえなかった。 これが、軽井沢夏の宴でのぎりぎりの妥協であった。*[12]
すなわち、辻井喬が本体であって、堤清二は仮の姿であった、とでも言うかのように、辻井さんは、引退後、辻井喬の名前で旺盛な執筆活動に勤しみます。
無論、文学者としての辻井喬の意味や価値は独立したものとして現代日本文学の屹立することは言うまでもありません。しかしながら、あれほど一世を風靡した、というよりも、まさに、時代を変えた、世界を変えた、とでもいうしかない、堤清二のセゾンでの活動は、――本人は言下に否定するでしょうが、あるいは文学者・辻井喬の存在を圧倒的に超えているのではないか、あるいはそれを包含しているのではないかと思うのです*[13]。
その意味で、御厨さんたちが、執拗な執念とでも言いたい、尋常ならざる強い思いで辻井喬ではなく、堤清二の立場での言葉を引き出したのは特筆に値すると思われます。
本書はその意味でも、堤清二という稀代な実業家、というよりも、途轍もなく巨大な楼閣と、それを囲繞する街や村を創造しようとした人間の、或る種の実像のようなものに限りなく迫った作品であると言えます。
3 存在論的自己否定
三浦雅士さんは、辻井喬さんの代表作は、二つの『沈める城』*[14]であるとおっしゃっています*[15]。二つというのは詩集と長篇小説で同名の作品があるからです。
それにしても「沈める城」とは、なんと予見的な作品名でしょうか。セゾン・グループの最盛期に、既に、自らが創造した企業群体が沈んでしまうことを予想していたのでしょうか?
あるいは、自らの内的イメージに符合させんがために、無意識に会社崩壊の引鉄を引いたとでも言うのでしょうか。無論、そんなことがあろうはずはあり得ません。しかしながら、強迫観念、と言っても無意識、と言ってもいいのですが、総じて、人をして、その行動を暗黙の裡に縛るものとは、得てしてそういうものなのかも知れません。
セゾングループには外部の専門家に委託した、大部の社史のシリーズがあります*[16]。
その中で、三浦雅士さんが、「セゾンとはニヒリズムの企業である」*[17]と述べているそうです。この三浦さんの発言に対して、堤さんは、それを「もっともなことだ」とした上で、こう述べています。
つまり会社のなかでの私の発言は、「自分が損するようなことをやったら、だいたい成功する時代だよ」ということだったのです。*[18]
この言い方は、あたかも「損して得取れ」や、「情けは人の為ならず」的な、卑近とも言える日常の道徳を述べているようにも思えますが、――無論、堤さんの行動の基幹には「人のためになる」*[19]という倫理観が存在していることは言うまでもありませんが、そのような、言ってみれば道徳的な「自己否定」ではなく、存在論的な「自己否定」があるような気もするのです。
先の堤さんの発言を受けて、橋本さんは「この時代の堤さんの戦略は終始一貫して自己否定です。」と指摘します。
すなわち、セゾングループは、というよりも堤清二という企業人は、徹底的に、それまでの自身の仕事を否定し、その上に新たな課題を発見し、それを解決する形で、次の仕事が構築されてきた、とも言えます。
具体的に言えば、「西武百貨店」を否定する形で、量販店(スーパーマーケット)「西友」や、「ファッション・ビル」つまりは場所を提供するテナント・ショップである「PARCO」を生み出し、あるいは、それらを否定する形でコンヴィニエンス・ストア「ファミリー・マート」を生み出します。そして、最終的にはブランドを否定する、ノン・ブランド商品の開発と販売を手掛ける「無印良品」にまで辿り着きます。
4 資本制システムとセゾンの無限拡張運動
これをして、鷲田さんはこう述べます。
しかし自己否定という概念はものすごく徴妙です。企業精神のフィロソフィー (哲学)としては自らを模倣したらもう終わりでしょう。 ただ、多くの画家やファッションデザイナーは、 一つ当たると自分のスタイルを模倣して数年間しのぐところがある。けれど、自己模倣は、創造にとってはいちばん危ない。だからこそ、自己否定はフィロソフィーになりうる /それはフィロソフィーであると当時に、モードの論理でもある。つまり前のシーズンと違うことを絶えずしつづける。止まったら終わり。だからセゾン・カルチャーは自己否定のフィロソフィー、モードの論理で、あるいはその背後にある資本主義の論理、つまり絶えず拡張しなければならない論理で動くのか、いずれにせよ、そういうもののなかにいやがおうにも呑み込まれる。その非常に徴妙なところで、 堤さんは舵取りをせざるをえなかったと思うのです。*[20]
堤さんが、最後に手がけた事業の一つがノンブランドたる「無印良品」でした。彼は、それを「反体制商品」*[21]だと言っていますが、「結果的にノーブランドというブランドになってしまった。」*[22]と堤さん本人が言うように、自己否定の運動に組み込まれた「反体制」は、それすらも「体制」、というよりも或るシステムと組み込まれていったのではないでしょうか。
鷲田さんがおっしゃっていることと同じことになりますが、社会学者の上野千鶴子さんも同様のことを述べています。
セゾンについては、つねにシニフィエよりもシニフィアンの方が過剰である。それは商品よりも貨幣の方がつねに多い慢性インフレ状態の資本主義市場と似ている。そして信用を先送りしながら貨幣を発行し続ける資本主義同様、セゾンもまた、この運動をやめるわけにはいかないのだ。セゾンという一企業集団について語ることは限りなく資本主義について語ることと似ている*[23]
5 「あれ、私がやっていることは、いったい何だろう。」
恐らく、堤さん自身が本来的に持っている「自己否定」感とでも言うべきものが、まさに20世紀後半の大衆消費社会のシステム、それすなわち資本制経済のシステムとマッチしたことにより、セゾンという、未曽有のイメージの帝国が誕生し、短期間で、敢え無く崩壊していったのでしょう。この崩壊の根元にもやはり「自己否定」の運動の時限装置が埋め込まれていたのではないかと思うのです。
堤さんは、こうも述懐しています。
「あれ、私がやっていることは、いったい何だろう。本当にいいことをやっているのか、どうなんだ」という疑問を持ちだしたのは、八〇年代に入ってからです。*[24]
80年代、と言えば、1980年に「無印良品」が誕生します。翌81年にコンヴィニエンス・ストア「ファミリー・マート」が設立され、更にその翌年82年には西武百貨店池袋本店が百貨店の年間売り上げ第一位を獲得します。言うなれば、全国制覇、天下を取ったにも等しい業績です。
全く以て素晴らしい、と言いたいところですが、その同じ82年に、詩集『沈める城』*[25]が刊行されているのです。
堤さんは、天下を統一した自らの城が、安土城のように焼け落ちるのではなく、密かに、水の中に沈んでいくヴィジョンを目にしていた、ということになります。
穿った見方をすれば、堤清二は、水中に沈めることこそが目的で、営々と自らの城を築いてきたのではないか、というのは、部外者であるわたしの単なる妄想であるに違いありません。
参照文献
セゾングループ史編纂委員会 (編). (1991年). 『セゾンの活動――年表・資料集』. リブロポート.
三浦雅士. (2016年). 「二つの名前を持つこと」. 著: 菅野昭正 (編), 『辻井喬=堤清二――文化を創造する文学者』. 平凡社。
三浦展. (2004年). 『ファスト風土化する日本――郊外化とその病理』. 洋泉社新書y.
三浦展. (2005年). 『下流社会――新たな階層集団の出現』. 光文社新書.
上野千鶴子, 中村達也, 田村明, 橋本寿朗, 三浦雅士. (1991年). 『セゾンの発想――マーケットへの訴求』. (セゾングループ史編纂委員会, 編)
村上春樹. (1996年). 「トニー滝谷」. 著: 村上春樹, 『レキシントンの幽霊』. 文藝春秋.
辻井喬. (1969年). 『彷徨の季節の中で』. 新潮社.
辻井喬. (1982年). 『沈める城』(詩集). 思潮社.
辻井喬. (1998年). 『沈める城』(長篇小説). 文藝春秋.
辻井喬. (2009年). 『叙情と闘争――辻井喬+堤清二回顧録』. 中央公論新社.
辻井喬, 上野千鶴子. (2008年). 『ポスト消費社会のゆくえ』. 文春新書.
堤清二. (1985年). 『変革の透視図――脱流通産業論』. トレヴィル.
堤清二, 三浦展. (2009年). 『無印ニッポン――20世紀消費社会の終焉』. 中公新書.
堤清二, 辻井喬. (2015年). 『わが記憶、わが記録――堤清二×辻井喬オーラルヒストリー』. (御厨貴, 橋本寿朗, 鷲田清一, 共同編集) 中央公論新社.
不明. (2024年). 「無印良品について」. 参照日: 2024年5月19日閲覧, 参照先: 無印良品: https://www.muji.com/jp/about/?area=footer
由井常彦, セゾングループ史編纂委員会 (共同編集). (1991年). 『セゾンの歴史――変革のダイナミズム』上下. リブロポート.
🐤
7,191字(18枚)
20240528 2108
*[1] 「オーラル・ヒストリー (oral history) あるいは口述(こうじゅつ)歴史(れきし)とは、歴史研究のために関係者から直接話を聞き取り、記録としてまとめること。政治史・労働史・地域史などのように、歴史研究の方法としてフィールドワークの伝統が根づいているところや、学際的な交流がなされてきた研究領域で発展してきた。出自は1920年代の都市社会学におけるシカゴ学派のライフストーリーの方法論にたどることができる。」(Wikipedia)。
*[2] 御厨「堤清二が辻井喬か、辻井喬が堤清二か、謎解きに迫る」/ [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]。
*[3] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]303頁。
*[4] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]305頁。
*[5] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]305頁。
*[6] 「政策研究大学院大学のオーラル・ヒストリープロジェクトの報告書」/ [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]299頁。
*[7]「記録はとるが整理はせず冊子化しないという厳しい条件つきだった。」御厨「堤清二が辻井喬か、辻井喬が堤清二か、謎解きに迫る」/ [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]303頁。
*[9] 「米荘閣」。この時はセゾングループの迎賓館の役割を果たしていましたが、グループ崩壊時に売却。現在は高級マンションが建っています。
*[10] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]264頁-269頁。
*[11] [辻井, 『本のある自伝』, 1998年]、 [辻井, 『叙情と闘争――辻井喬+堤清二回顧録』, 2009年]などでは、このビジネスの側面が巧妙に隠蔽、あるいは忌避されているような気がします。まあ、それは当然と言えば当然ですね。
*[12] 御厨「堤清二が辻井喬か、辻井喬が堤清二か、謎解きに迫る」/[堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]304頁。傍線引用者。
*[13] そのような観点からも辻井喬の作品群を検討すべきではないかと考えています。
*[14] [辻井, 『沈める城』(詩集), 1982年]、 [辻井, 『沈める城』(長篇小説), 1998年]。
*[16] [由井 セゾングループ史編纂委員会, 1991年]、 [上野, 中村, 田村, 橋本, 三浦, 1991年]、 [セゾングループ史編纂委員会, 1991年]。
*[17]三浦「生ける逆説――文化・芸術戦略批判」/ [上野, 中村, 田村, 橋本, 三浦, 1991年]/ [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]130頁から援引。
*[18] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]131頁。
*[19]辻井の発言/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]43頁。
*[20]鷲田の発言/ [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]131頁。
*[21] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]133頁。
*[22] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]133頁。
*[23] 上野「イメージの市場――大衆社会の「神殿」とその危機」/ [上野, 中村, 田村, 橋本, 三浦, 1991年]136頁/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]11頁-12頁より援引。