6

沈める城
セゾングループは何故崩壊したのか?
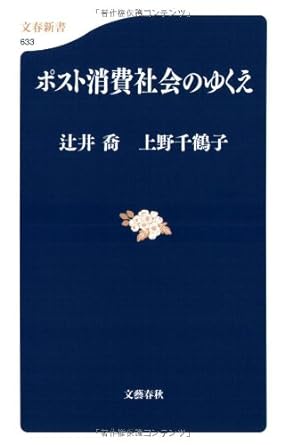
■辻井喬・上野千鶴子『ポスト消費社会のゆくえ』2008年5月20日。
■対談(流通産業・消費社会・現代史・現代文学)。
■全4章・324頁。
■2024年5月31日読了。
■採点 ★★★★★。
- 「セゾングループ」なる名称は1990年から使用されている。したがって、それ以前については「西武百貨店」なり、「西武流通グループ」なりと、時代ごとに、名称を使い分けねばならないが、本稿では、煩瑣を避けるために、通時的にも一貫して「セゾングループ」という企業群体に仮称させることをご了承頂きたい。
- 傍線部は断りがない限り、全て引用者による。
目次
セゾングループ失敗の原因 第二:グループ内の一部の失敗が波及した... 16
セゾングループ失敗の原因 第三:堤清二の経営責任... 19
セゾングループ失敗の原因 第四:堤清二のパーソナリティ... 21
1 かつて、百貨店というものがあった。。。。。。
今となっては、昔のことですが、かつて、百貨店、デパートメント・ストアは夢の国でした。家族の憩いの場であり、子どもたちにとっても月に一度ぐらい訪れる至福の場所でした。仮に買い物をしなくても、夢のような商品を見て回る、屋上の遊園地で遊ぶ、その下にあったであろう食堂で昼食を取る。丸一日いても飽きない、まさに魔法のような空間でした。
しかしながら、ご存知のように、今や百貨店は長期的な凋落の中にあり、次々と閉店、経営縮小の途を取らざる得なくなっています。
言うなれば、かつて百貨店が、その名の通り、100パーセント引き受けていた、ありとあらゆるアミューズメントが分散し、今や誰も百貨店にその目的を要求しなくなったのだと思います*[1]。
単に商品を購入するという面でも、格安のスーパー・マーケットがあり、値段は少々張るかも知れませんが、24時間営業していて、日常的に必要なものはおよそ何でも手に入るコンヴィニエンス・ストアがあり、更には、送料は掛かるかも知れませんが、必要だと思う商品をピン・ポイントで必要な分だけ購入できるネット・ストアが隆盛を誇る今となっては、個人的には残念ですが、百貨店にその存在価値を見出すことは極めて困難ではないかと思います。
時間の問題だとは思いますが、恐らく百貨店という小売形態は滅亡するか、極めて少数の大百貨店だけが残るのではないでしょうか。
本書は、その百貨店の凋落を文字通り、身を以て体験した、西武百貨店、というよりもそれを包含するセゾングループの経営者であった堤清二さん、――いや、ここではその詩人・小説家としての辻井喬さんが「代理」として登場されていますが*[2]――と、社会学者の上野千鶴子さんの対談です。
一言でいうと、辻井さんには大変申し訳ないですが、本書は尋常ならざる面白さでした。
要は、時代の最先端を行き、あれほどの隆盛を誇ったセゾングループが、バブル経済の崩壊があったにせよ、何故、ああも簡単に
崩壊してしまったのだろうか、という問いに相当緻密に答えようとしていることです。その執念の主たる部分は上野さんの側にありますが、こんなにも、自らに分の悪い対談、――というか、見方によっては「取り調べ」のような企画――など断ってもよかったはずなのに、これに真摯に応えようとしている辻井さんの方がその辛さから言って、言わば精神力の勁さのようなものが要求されたのではないでしょうか。
実は同じような企画*[3]が先行していましたが、それに関しては、辻井さんは生前、刊行を禁じていました。この間に、何か心境の変化でもあったのでしょうか?
元々、堤さんは、自らの仕事を客観化しようという意思がありました。全6巻となるセゾングループ社史である『Série SAISON』です。「社史」であるにも関わらず外部の専門家たちに委託し、第三者の視点からセゾンという企業を捉えようとしました。本書についても、そのような思いがあったのかも知れません。セゾングループの社史『Série SAISON』全6巻の内訳は以下の通りです。いずれもリブロポートから1991年から92年にかけて刊行されたものです。
巻末に、目次についてもご紹介いたしましたが、一企業の社史を編纂するに際して、外部の各専門家に委託し、学問の対象として一企業の歴史とその活動を分析、研究する、という、極めて前代未聞の形が取られました。当然、それは「社史」という枠を大幅に超えて、資本制経済史、社会史、もっと言えば文明史の中に、セゾンという企業群体の意味と、その位置づけを探ろうとする試みだったのです。
それを提案、リードしたのが、事実上のグループ創業者であった堤清二さんその人に他なりません。
この社史の企画が出された1980年代末には、自己の経営する会社群への客観的な視座を堤さんが持っていたことを意味しています。
『Série SAISON』が、セゾングループの最盛期における分析ですから、言ってみれば、セゾンの「成功」について書かれている訳ですが、本書は、むしろ、その逆で、セゾンにおける「失敗」の研究と言ってもよいでしょう。
高名な共同研究に『失敗の本質――日本軍の組織論的研究』*[4]がありますが、まさに、本書は『失敗の本質――セゾングループの社会学的研究』の予備対談のような趣があるという気がします。
2 資本制経済システムとセゾングループの興亡
さて、1940年に池袋に誕生した「武蔵野デパート」は、戦後49年に、現行の「西武百貨店」と名称を変え、その後、店長に堤清二さんを迎えると、着実にその業績を伸ばしていきました。1982年には池袋本店が百貨店売上高全国1位を、87年には西武百貨店全体として百貨店売上高全国1位を成し遂げました。言うなれば、「全国制覇」を成し遂げた、ということになります。
1985年には、従来「西武流通グループ」といった名称を「西武セゾングループ」と変更し、更には90年にはそれをまた「セゾングループ」と変えました。
しかしながら、その後、バブル経済の崩壊とともに、グループ企業の「東京シティファイナンス」、及び「西洋環境開発」の経営破綻の影響がグループ企業全体へと及び、ついに2000年にグループは解体への道を歩んだのでした。
今でも、まだ西武百貨店は「西武」と名称を変えて残っていますし、グループ企業であった「PARCO」や「西友」あるいは「無印良品」などは、バラバラにはなっていますが、それぞれ独自の路線で生き残ってはいます。
とは言うものの、往時のセゾングループの隆盛を知るものからすれば、まさに隔世の感、とはこのことでしょう。
一体全体、このセゾングループの勃興と滅亡は、単に一企業の問題なのか、いや、そうではなく、20世紀後半の消費社会、資本制経済システムの広がりと深化という現象の典型例だったのか、仮に
後者だとすれば、まさにセゾングループを考えることは資本制経済システムについて考えることに等しいという訳です。
本対談(というよりもインタヴューという方が妥当かも知れませんが)の対談者の一人、上野千鶴子さんは、「まえがき」としてこう書かれています。
セゾンについては、つねにシニフィエよりもシニフィアンの方が過剰である。それは商品よりも貨幣の方がつねに多い慢性インフレ状態の資本主義市場と似ている。そして信用を先送りしながら貨幣を発行し続ける資本主義同様、セゾンもまた、この運動をやめるわけにはいかないのだ。セゾンという一企業集団について語ることは限りなく資本主義について語ることと似ている*[5]
要は、セゾングループは極めて「資本主義」的だった、ということに尽きるということです。まさにおっしゃる通りだと、わたしも思います。
実をいうと、この引用文は、直截、本書『ポスト消費社会のゆくえ』のために書かれたのではなく、以前書かれた論文の一節からの自己引用でした。それは、先に述べたセゾングループ社史である『Série SAISON』の中の一冊『セゾンの発想』*[6]に書き下ろされた「イメージの市場――大衆社会の「神殿」とその危機」という論文からのものでした。この段階では、まだセゾングループは崩壊の芽すら全く出ておらず、最盛期の真っただ中のことでした。
3 セゾングループは何故崩壊したのか?
一体、セゾンの栄光と没落は何を意味していたのでしょうか。
おそらく、今となってはそのことに関心を持つ方々は極めて少ないと思います。
「セゾン」というネイム・ヴァリューも急落して、あるいは企業の固有名詞としては死語に近い状態になっているのではないでしょうか。
本書は、全4章の構成を持ち、セゾングループの前史から、その興隆期、さらにはその解体期までを歴史的に順を追って考察を進めていきます。
セゾンという企業のコアとなるべきものついては、恐らくその隆盛期における様々な活動についても検討せねばなりませんし、本書でも興味深い逸話が多く語られています。そこまでが本書の半分のページが割かれていますが、問題は、後半の半分のページのさらに半分の「第三章」にあります。先にも触れましたが、「失敗の研究」ということになります。
上野さんは、セゾングループの失敗による解体の理由について4つの仮説を立てて、順を追って検討していきます。
4つの仮説とは以下の通りです。
上野さんは、この4つの原因を上げる前提として、そもそも、堤清二の経営責任を問えるのか、という疑問から発している、ということを述べています。
(【引用者註】上野さんがNHKの『わが挫折を語る 日本企業への教訓』*[7]という番組に出演したのは)世間は「セゾングループの失敗は総帥・堤清二の失敗だ」と言うけれども、一体どの企業がバブル崩壊を予測して、そのダメージを避けることができたのか、という疑問があったからです。(中略)つまり時代の抗いようのない変化にのまれたとき、堤清二を責める権利は誰にあるのかという疑問があって、私はこの番組に出演しました。*[8]
その意味では、本書も、広い意味での「堤清二擁護説」*[9]を取っているとも言えます。
4 セゾングループ失敗の原因
では、順を追って確認していきましょう。
セゾングループ失敗の原因 第一:グループの体質
1960年代に勃興し、80年代には覇権を手中に収めた西武百貨店を基幹企業とするセゾングループですが、旧来の伝統的な百貨店の経営者たちや、あるいはその顧客たちから見ると、あるいは白眼視されていたかも知れません。言ってみれば、虚飾に彩られて、実質が伴わない、砂上の楼閣のように見えていたかも擦れません。
ここにはいろいろな意味があるのだと思いますが、一つには、セゾンが創業の当初から「借金体質」*[10]だったということもあります。上野さんはこう述べます。
セゾンの成長期は「リスクをとって拡大する」という成長型DNAが埋め込まれていました。このDNAがあったから、バブルの崩壊で躓いたときのセゾングループのつんのめり方が大きかったというのが、私の解釈ですが。*[11]
つまり、この「リスク」というのが「借金体質」だったということになります。
しかし、本書では、この項では述べられていませんが、セゾンのDNAとは何かを考えると、情報発信が先行する形での小売り業だったのではないでしょうか。
80年代に最も先鋭的な広告宣伝を行っていた企業の一つがセゾングループでした。まさに、これこそ、上野さんがいみじくも述べる「つねにシニフィエよりもシニフィアン(*[12])の方が過剰である。」*[13]という発言と符合するところでしょう。つまり、実態よりも過剰な情報が付加されて、それが合金(アマルガム)として、価格が吊り上げられた商品として、販売されるのです。いわゆるブランド物の商法とはそういうものですが、それを牽引したのが西武百貨店だったのです。西武百貨店は多くのブランドとライセンス契約を結び、それらを日本に紹介したことで知られています*[14]。つまり、ブランドというラベルは単なる情報にしか過ぎません。しかし、消費者は、その情報に高いお金を払っていたのです。「情報の商品化」*[15]という訳です。わたしたち消費者は「商品ではなく、情報を買っているわけです。」*[16]
つまり、このイメージ戦略による「情報の商品化」こそがセゾンの、よく言えばDNA、平たく言えば体質ということにならないでしょうか。
「バブルの経済」については、また別途触れねばなりませんが、言ってみれば、セゾンは、期せずして、この「バブルの経済」の波に乗ったのです*[17]。そして、波が去ったあとは、見事に泡となって消えた、ということになります。まさにセゾンこそバブルの経済を象徴する企業ではなかったではないでしょうか。
無論、そのことは辻井さん自身も百も承知だったはずです。
ブランド物を売り続けることの罪の意識からなのかは分かりませんが、1980年には、今に連綿と続く、ノンブランド商品である「無印良品」の販売が始まっています。これは今や世界に広がっている、大変なヒット商品群だったのです。
また、借金の問題についても、各グループ企業のトップには注意を促したことを辻井さんは述べています。
金融機関の言いなりになって、ほいほいお金を借りては絶対いけない」、「土地転がしは絶対するな」と注意を促した記憶があります。ところが、グループの幹部はこの注意を見事に守らなかった。*[18]
すなわち、これが、第二の原因となります。
セゾングループ失敗の原因 第二:グループ内の一部の失敗が波及した
一般的には、セゾンの崩壊の直接的な理由として挙げられるのが、不動産会社(?)「西洋環境開発」の失敗が余りにも大きく、グループ本体にまで波及した、ということになっているようです。
上野 セゾングループは、西洋環境開発と東京シティファイナンスの多額の負債が引き金となって、小売業でも不良債権を抱えた部門の清算や売却を迫られ、グループ全体が解体という道を辿っていくことになります。一番の命取りは、やはり西洋環境開発でしょうか?
辻井 両方いい勝負じゃないでしょうかね。でも損害の額からいったら東京シティファイナンスのほうが大きいですよ。(中略)しかし、この二つの会社でグループは解体せざるを得なくなった。*[19]
意外に東京シティファイナンスの損害が大きかったようですが、いずれにしても辻井さんがおっしゃっているように、この二社の波及が相当に大きいものだったということになります。
本書ではグループ内企業の失敗例を5つ挙げて説明しています。
いずれも本業たる百貨店、あるいは小売業という流通産業から離れた、土地、建物に付随するサーヴィスを商品とする、広い意味での「不動産業」、あるいは「金融業」での失敗、ということになりますが、まさに「バブルの経済」に竿を差した企業展開だったと言えます。言うなれば、転ぶべくして転んだ、とも言えますが、それぞれの企業トップの経営手腕がかなりお粗末だったということと、それを見破ることができなかった辻井さんの経営責任も当然あったのだと思います。
セゾングループ失敗の原因 第三:堤清二の経営責任
堤さんに経営責任がないはずはないので、当然と言えば当然なのですが、この問題は、原因の第四にあたる「堤清二のパーソナリティ」とも連動する問題だろうとは思います。言ってみれば、これもセゾンの体質、と言っても過言ではないかも知れません。
例えば、先の原因の第二の中に上げた「西洋環境開発グループ」の失敗は、それらの各企業体のトップの失敗ですが、それは、彼らが、或る種、堤さんの体質を忖度した結果とも言いうるかも知れません。「長期滞在型休暇」を前提としてデザインされた「サホロリゾート」など、誇大妄想としか言いようがない――現在も、その当時も日本においてそのようなライフスタイルが可能な層がどれくらいいたというのでしょうか? ――ですが、堤清二の構想の基底にあるものは、まさにこの「誇大妄想」ではなかったでしょうか? 街を新たに作ろうとした「つかしん」然り、「タラサ志摩」の「巨大な殿堂」*[20]のような建造物然り。
上野さんはこれについて、こう述べています。
辻井さんは、採算を度外視して投資をなさる方だという考え方が、社員に定着していたのではないでしょうか。(中略)権力の追随者というものは、権力者の意向を過剰にくみ取って、権力者の意向以上に突出しがちなものです。*[21]
それに対し、辻井さんはこう述べます。
彼ら(*[22])は、私の企業理念をまったく理解しないで、私への思い込みだけで過剰に反応していたんだと思います。だから「立派にしないとご機嫌が悪いよ」という話になってしまうんです。*[23]
要は、上野さんがいみじくも語るように「辻井さんのお考えに、経済合理性があると思われていなかったのではないでしょうか?」*[24]ということだったのかも知れません。
辻井さんの、多角的に経営の手を拡げる、それも流通業とは異なる異分野への拡大、――とりわけ美術館や劇場などの文化的な施設への投資を見れば、あたかも、辻井さんが趣味的に金を使っていると見られてもおかしくはなかったのではないかと思います。
セゾングループ失敗の原因 第四:堤清二のパーソナリティ
そもそも、辻井さんは経営者として適格だったのでしょうか? それについてはわたしには分かりません。たまたま偶然のように、百貨店の店長となり、後発故の不利を挽回するために、辻井さんの独自の感性と理念を活かして急成長しましたが、それはまさに、当時の日本の置かれていた経済状況の好調と符合していた訳です。その波が去ってしまえば、当然経営的にも苦戦に追い込まれるのは必然だったかもしれません。それは多くの日本企業が軌を一にして経験したことですが、セゾングループはとりわけそのプラスとマイナスが極端な形で出たということになります。
しかしながら、それにしても、セゾングループの急落はいささか腑に落ちません。一体、何が他社と違っていたのでしょうか?
本稿は「沈める城――辻井喬/堤清二」という通しタイトルを持ちます。いうまでもなく、「沈める城」とは、1982年に刊行された詩集であるとともに、1998年に同題で刊行された長篇小説のことです。
かつて、わたしは、辻井さんにとっての、この「沈める城」のイメージについて次のように書いたことがあります。
80年代、と言えば、1980年に「無印良品」が誕生します。翌81年にコンヴィニエンス・ストア「ファミリー・マート」が設立され、更にその翌年82年には西武百貨店池袋本店が百貨店の年間売り上げ第一位を獲得します。言うなれば、全国制覇、天下を取ったにも等しい業績です。/全く以て素晴らしい、と言いたいところですが、その同じ82年に、詩集『沈める城』が刊行されているのです。/堤さんは、天下を統一した自らの城が、安土城のように焼け落ちるのではなく、密かに、水の中に沈んでいくヴィジョンを目にしていた、ということになります。/ 穿った見方をすれば、堤清二は、水中に沈めることこそが目的で、営々と自らの城を築いてきたのではないか、というのは、部外者であるわたしの単なる妄想であるに違いありません。*[25]
つまり、辻井さんは自らの破滅のイメージに無意識に合わせる形で、起業家としても、そのように行動してしまったのではないか、ということです。そんな馬鹿な、と思うところですが、何しろ無意識ですから、ご本人の責任をどれくらい問えるかは難しいところです。
実はこの問題を、既に指摘されていた方がいます。辻井さんとも対談されている三浦展(みうらあつし)さんです。上野さんはその三浦さんとの対談集『消費社会から格差社会へ』*[26]を上梓されています。
本書では上野さんによって、こう紹介されています。「セゾングループはなぜ失敗したのか」という問題について、
彼は、堤さんの「破滅への願望が、こういう事態を招いたというか、意図的に惹き起こしたというか」と述べています。これは彼の卓見だと思います(。)(中略)三浦さんはその対談で、いくつか印象的なキーワードを述べています。辻井さんのあの失敗は「確信犯だ」。それから辻井さんには「死への衝動」があると。*[27]
辻井さん、本人も、半分冗談だとしても、「なるほど。それはいいこと言ってる。」*[28]と言ってるぐらいですから、多少なりとも正鵠を射る点があったのかも知れません。
会社経営者としてはとんでもない、はた迷惑な話ですが、芸術家として考えれば全くあり得ない話でもありません。すなわち、堤清二がセゾングループの経営をしていた訳ではなく、その上位パーソナルであるところの辻井喬が、芸術創造として、その作品として企業の経営をしていたのだと考えれば得心がいきます。
陶芸家が納得のいかない作品を惜しげもなく破壊するように、辻井さんも、自らの企業理念から逸脱した企業群を破壊した、ということなのでしょうか?
①11,645字(30枚)
【参考資料】
③『セゾンの発想――マーケットへの訴求』目次
1 イメージの市場 大衆社会の「神殿」とその危機(上野千鶴子)
池袋店9期と「イメージ戦略」
成熟消費社会と百貨店の文化化
パルコ 西武よりも西武的な
八〇年代グループ拡張とCI戦略
結論
2 研ぎすまされたドン・キホーテ 生活者への提案(中村達也)
消費社会の現在
セゾングループからのメッセージ
3 「カベ」への挑戦 地域への対応(田村明)
地域と企業
セゾングループの地域へのかかわり
街づくりへの挑戦
可能性と限界
都市の時代の街づくりとその担い手
4 無戦略の漂流から 多角化の論理(橋本寿朗)
セゾンの経営と時間の観念 序にかえて
西友ストアーの創設
クレジットカードビジネスの開拓
外食産業の新生
企図の慎重な実現 一つの総括
5 生ける逆説 文化・芸術戦略批判(三浦雅士)
変化
スーパーマーケット
キャッシュ・レジスター
アメリカ
物語
大衆の変容
文化戦略批判
批判と反批判
イロニー
ミダース王の手
クリエーター一覧
④『零の修辞学――歴史の現在』目次
吉見俊哉「シミュラークルの楽園──都市としてのディズニーランド」
大島洋「Fax NUDE 東京1992」
片木篤「個室のユートピア」
森下みさ子「占いのディスクール」
生井英考「デザイン、消費文化の上演」
山田登世子「誘惑ゲーム──性とモードの現在」
伊藤俊治「記憶装置の変容──美術館革命とマルチメディア動向を中心に」
多木浩二「デザインの社会」
松田行正「CONTAINER」
森下みさ子「作動する「教育」装置──空なる記号の場」
多木浩二「スポーツという症候群」
多木浩二「あとがき」
目次 1 近代性の構造
機械
自然の機械化
宇宙模型としての機械
身体の機械化
自動装置
精神の機械化
精神という実験
感性の機械化
機械の美学
社会の機械化
機械状組織
トランスモダンの作法1
ファルマコン装置
「ロゴス」のメタモルフォーゼ
〈私〉の戦争機械
崇高1
顔
眼と永遠
2 近代性の構造
方法
知の方法
発見的知性
支配の方法
主人と奴隷
方法のエチカ
自律の空間
方法と術
アルス変容
方法の外部
漂流の技法
トランスモダンの作法2
反方法
追憶と追悼
〈純粋〉というレトリック
雑種の精神
エチカ・ネガティーヴァ
軟体構築
夢見る力
3 近代性の構造
交通
装置の体系
分割の装置
分身たちの共同体
訓練の装置
時間の牢獄
統合の装置
飼いならされた自然
加速する装置
次元の消滅
トランスモダンの作法3
群衆
間
内なる異者へ
「声の風」あるいは書物の解体
homo viator
貨幣について
嗅覚の政治学
4 近代性の構造
労働
労働と倫理
労働社会の到来
労働と技術
労働と消費
流通する身体
労働と自己
資本主義的人間
労働と蓄積
記憶の外部化
トランスモダンの作法4技術時代と遊戯の精神
Ontopoietik
崇高2
人生の日曜日
不幸計算
ニヒリズムとシュールユマン
宇宙の美学
5 近代性の構造
時間
創造と時間
新しい時を求めて
直進する時間
時計仕掛けの進歩
時間の先取
企てる精神
モードの時間
〈いま〉の専制
時間の組織化
発明される発明
トランスモダンの作法5
未熟
物語・断章
空間の再発見
未来の廃墟
歴史の終焉
反歴史哲学
詳細目次
参照文献
セゾングループ史編纂委員会 (編). (1991年). 『セゾンの活動――年表・資料集』. リブロポート.
戸部良一, 寺本義也, 鎌田伸一, 杉之尾孝生, 村井友秀, 野中郁次郎. (1984年/1991年). 『失敗の本質――日本軍の組織論的研究』. ダイアモンド社/中公文庫.
三浦雅士. (2016年). 「二つの名前を持つこと」. 著: 菅野昭正 (編), 『辻井喬=堤清二――文化を創造する文学者』. 平凡社。
三浦展. (2004年). 『ファスト風土化する日本――郊外化とその病理』. 洋泉社新書y.
三浦展. (2005年). 『下流社会――新たな階層集団の出現』. 光文社新書.
上野千鶴子, 三浦展. (2007年). 『消費社会から格差社会へ』. 河出書房新社.
上野千鶴子, 中村達也, 田村明, 橋本寿朗, 三浦雅士. (1991年). 『セゾンの発想――マーケットへの訴求』. (セゾングループ史編纂委員会, 編)
村上春樹. (1996年). 「トニー滝谷」. 著: 村上春樹, 『レキシントンの幽霊』. 文藝春秋.
鳥の事務所. (2024年5月28日). 「まさに「沈める城」ではないか――辻井喬ではなく、堤清二を追い詰める」. 参照先: 『鳥――批評と創造の試み』: https://torinojimusho.blogspot.com/
辻井喬. (1969年). 『彷徨の季節の中で』. 新潮社.
辻井喬. (1982年). 『沈める城』(詩集). 思潮社.
辻井喬. (1998年). 『沈める城』(長篇小説). 文藝春秋.
辻井喬. (2009年). 『叙情と闘争――辻井喬+堤清二回顧録』. 中央公論新社.
辻井喬, 上野千鶴子. (2008年). 『ポスト消費社会のゆくえ』. 文春新書.
堤清二. (1985年). 『変革の透視図――脱流通産業論』. トレヴィル.
堤清二, 三浦展. (2009年). 『無印ニッポン――20世紀消費社会の終焉』. 中公新書.
堤清二, 辻井喬. (2015年). 『わが記憶、わが記録――堤清二×辻井喬オーラルヒストリー』. (御厨貴, 橋本寿朗, 鷲田清一, 共同編集) 中央公論新社.
不明. (2024年). 「無印良品について」. 参照日: 2024年5月19日閲覧, 参照先: 無印良品: https://www.muji.com/jp/about/?area=footer
野口悠紀雄. (1989年). 『土地の経済学』. 日本経済新聞社.
野口悠紀雄. (1992年). 『バブルの経済学―日本経済に何が起こったのか』. 日本経済新聞社.
由井常彦, セゾングループ史編纂委員会 (共同編集). (1991年). 『セゾンの歴史――変革のダイナミズム』上下. リブロポート.
13,130(33枚)
🐥
202406112002
*[1] 言うなれば、個人の欲望が個々に受容される形になりつつある気がします。テレ-ヴィジョンの地上波の放送は衰退し、ネットで好きな番組を好きな時間見ることが可能になりました。他の業種についても同様な現象が生じているのではないでしょうか? 例えば教育。学力や個々のニーズが全く異なる多人数の生徒を一ヵ所に集めて、蜿蜒と授業をする、という形態は徐々に崩れ始め、ネットで、自分の能力や、自分の知りたいことを、自分のスピード、自分のタイミングで学べるようになっていくのだと思います。これについては別稿を立てて論ずる必要があろうかと思います。
*[2] 恐らく、堤清二さんの上位パーソナルが辻井喬さんなのです。
*[3] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]。
*[4] [戸部, ほか, 1984年/1991年]。
*[5] 上野「イメージの市場――大衆社会の「神殿」とその危機」/ [上野, 中村, 田村, 橋本, 三浦, 1991年]136頁/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]11頁-12頁より援引。
*[6] [上野, 中村, 田村, 橋本, 三浦, 1991年]。
*[7] 2003年・NHK・「ETVスペシャル」。堤清二さんも出演していたそうです。
*[8] [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]172頁。
*[9]上野さんの発言/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]172頁。
*[10] 上野さんの発言「セゾングループの場合の「リスク」とは、何といってもその借金体質だったんですね。」/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]177頁。
*[11] [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]175頁。
*[12] 【引用者註】「シニフィアン(仏: signifiant)とシニフィエ(仏: signifié)は、フェルディナン・ド・ソシュールによってはじめて定義された言語学の用語。また、それらの対のことを、シーニュ(仏: signe)と呼ぶ。/概要/シニフィアンは、フランス語で動詞 signifier の現在分詞形で、「指すもの」「意味するもの」「表すもの」という意味を持つ。/それに対して、シニフィエは、同じ動詞の過去分詞形で、「指されるもの」「意味されているもの」「表されているもの」という意味を持つ。[フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』]。
*[13] 上野「まえがき」/[辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]11頁。
*[14] 辻井さんの発言「海外ブランドはほとんど私のところが導入しましたね。」/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]164頁。
*[15]上野さんの発言/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]167頁。
*[16]上野さんの発言/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]167頁。
*[17] 上野さんはこう述べています。「時代に乗っかった者は、必ず時代に追い越される、つまりマーケットから飽きられるときが、必ず来ます。」/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]106頁。
*[18]辻井さんの発言/ [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]176頁。
*[19] [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]193頁-194頁。
*[20] [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]183頁。
*[21] [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]184頁。
*[22] 【引用者註】セゾングループ内の各企業のトップ。
*[23] [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]185頁。
*[24] [辻井 上野, 『ポスト消費社会のゆくえ』, 2008年]185頁。
*[26] [上野 三浦, 『消費社会から格差社会へ』, 2007年]。